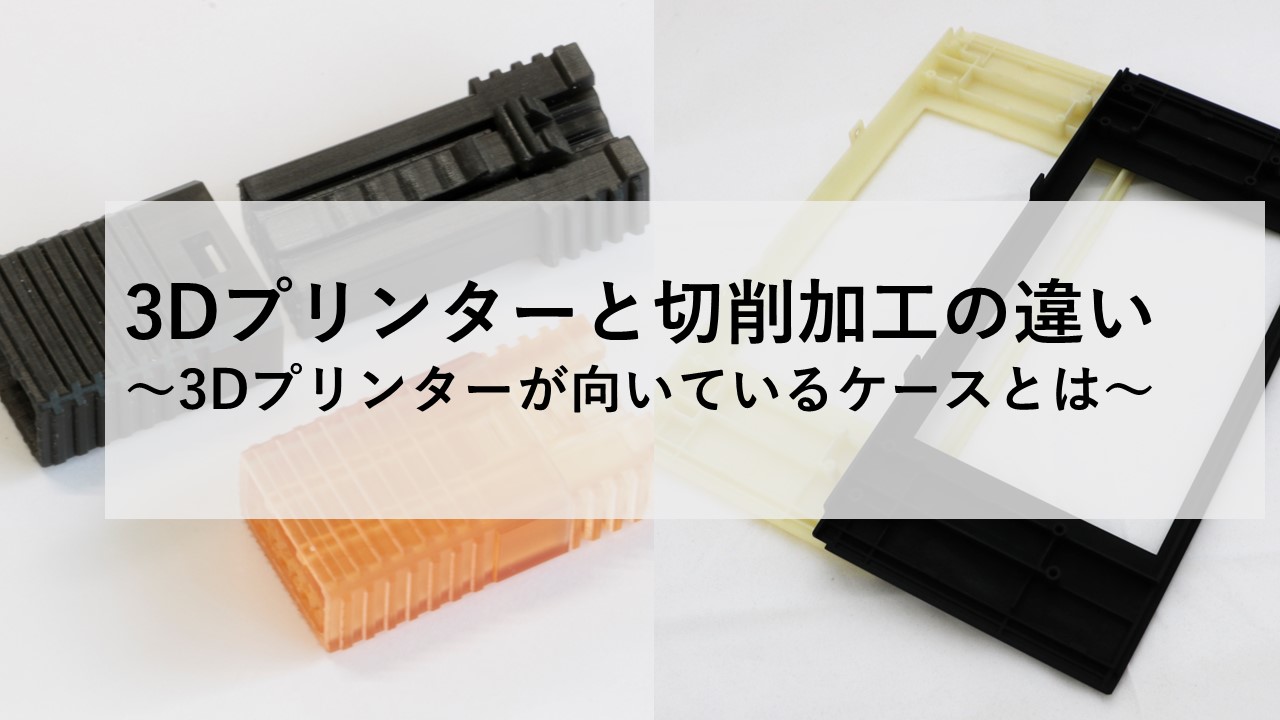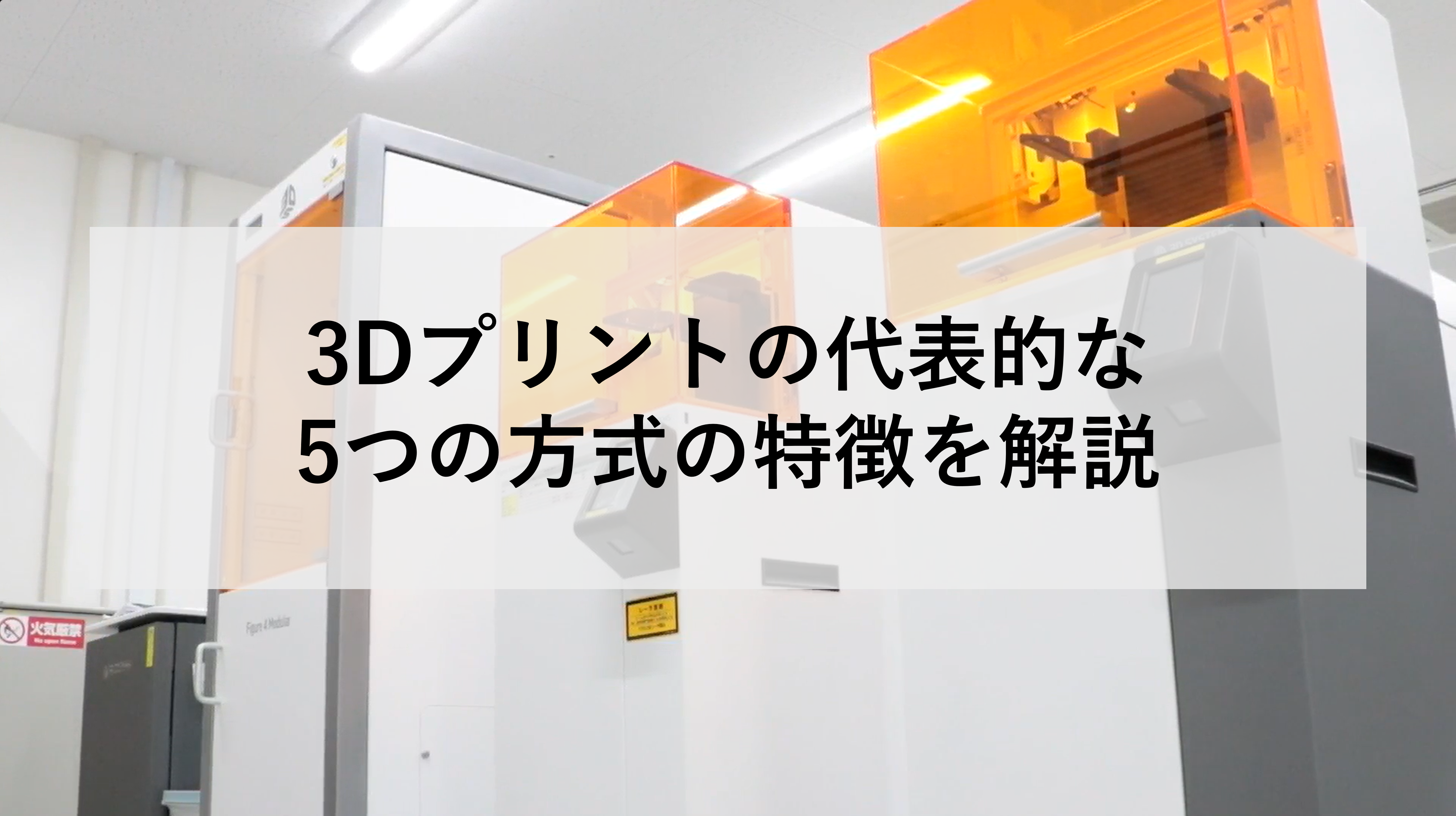筆者情報
- SOLIZEオンライン3Dプリント お役立ち情報編集部
- SOLIZEの3Dプリンター事業に従事する社員が、3Dプリンターの基礎知識や活用方法、活用例など、3Dプリンターに関する情報を発信します。 ・Twitter ・facebook
3Dプリントを利用したものづくりの手順
手軽に好みの形状のものを作れることから、3Dプリントは非常に人気があります。
よく知られている3Dプリンターの方式としては、液体樹脂に紫外線を照射して硬化させる「光造形方式」や、熱で溶かした樹脂を積み重ねていく「熱溶解積層方式」があります。その他にも、粉末状の材料に高出力レーザーを照射して焼結させる「粉末焼結方式」や、液状の紫外線硬化樹脂を噴射しながら紫外線で硬化・積層させる「インクジェット方式」なども使用されています。
使用される材料も樹脂だけでなく、金属やセラミックなど多種多様な素材が利用可能です。
3Dプリンターを選ぶ際には、使用する材料・求められる精度・予算などに応じて最適な機種を選ぶ必要があります。ただし、3Dプリントでモノを作るには、まず正確な立体データを作成することが不可欠です。
というのも、3Dプリンターは入力されたデータの形状に基づいて造形を行うため、データの正確さがそのまま出力物の品質に直結するからです。そのため、3D-CADや3D-CGソフトなどを用いて、誤りのない立体データを作成することが求められます。
また、3Dプリンターを使えば手軽に自由な形状のものが作れますが、出力前のデータ作成には十分な注意が必要です。
立体データが完成したあとは、それを3Dプリンターで読み込める形式に変換しなければなりません。この変換によって、データを正確にプリンターへ伝える準備が整います。
必要な材料を用意し、データを3Dプリンターに入力すれば、データ通りの形状のものが出力されます。
このように、正確なデータさえあれば、希望する形状の物を3Dプリンターで製作することが可能です。そのため、近年では、3Dプリンターを所有していない場合でも、データだけを業者へ送付し、造形を代行してもらえるサービスが広く利用されています。
3Dプリントで作ったモノをマスターモデルとして使う
高精度で製作できる3Dプリンターも存在するため、3Dプリントによって作られたモノは、さまざまな形で活用することが可能です。また、必要に応じて、さらに加工を加えることで、より高品質な仕上がりにすることもできます。
たとえば、表面に磨きをかけて鏡面のような仕上げにしたり、美しい塗装を施したりすることで、見た目の印象を一層引き立てることができます。
このように、3Dプリンターで作成したモノの仕上がりに満足できない場合には、後加工を施すことを検討するとよいでしょう。
さらに、より高品質な製品を目指す場合や、大量生産を行いたい場合には、3Dプリンターで作成したモノをマスターモデルとして活用するケースも多く見られます。
従来は、マスターモデルを工作機械で製作する際、熟練した技術や大型の設備が必要であり、作業を簡単に進められないことが少なくありませんでした。しかし、3Dプリンターを用いれば、短期間でかつ高い精度をもってマスターモデルを作ることが可能となります。
このように、3Dプリンターであれば、マスターモデルの作成を手軽に行うことができるため、図面やデータ上だけで確認するのではなく、実物を用いて仕上がりをチェックし、不具合があればすぐに修正を加えることができます。その結果、より完成度の高いマスターモデルを作り上げることが可能になります。
加えて、元となる設計データを修正すれば、短時間で再びマスターモデルを出力することができるため、試作と改善を繰り返すプロセスもスムーズに進みます。
図面上で入念にチェックしていたとしても、実際にモノができあがると予期せぬ不具合が見つかることも少なくありません。そのため、3Dプリンターで実物を製作し、事前に確認した上で次の工程へ進むことが、確実な製品づくりにつながります。
このように、より正確なマスターモデルがあれば、以降の工程においても精度の高い作業が可能となり、結果として高品質な製品の製造を実現できるのです。
切削・表面処理・鋳造などの工法の特徴
このように、従来の製作方法と3Dプリントを組み合わせることで、3Dプリンターの活用範囲はさらに広がります。
たとえば、切削や表面処理、鋳造などの従来の工法は、ある程度専門的な知識や経験を必要とする部分もありますが、基本的な内容であれば比較的容易に理解することができるでしょう。
まず、切削加工とは、切削用の工具を用いて、対象となるモノの不要な部分を削り取る加工方法です。具体的には、旋削・穴あけ・平削り・フライス削りなど、多くの切削方法が存在しており、それぞれに特徴があります。
この切削加工は、3Dプリンターで作成したモノを手直ししたい場合や、細部の調整を行いたい場合に非常に有効です。
次に、表面処理とは、めっきや印刷などを施すことで、外観や機能性を向上させる加工のことを指します。ただし、素材の種類によっては適用できる表面処理が限定される場合があるため、使用する素材と処理方法の相性について理解しておくことが重要です。
また、鋳造は金属などを高温で溶かし、液体状にしたものを型に流し込んで、目的の形状に成形する加工方法です。従来の鋳造工程では、まず木型を作成し、それをもとに砂型を製作し、そこへ溶かした金属を注ぐという手順が一般的でした。
しかし、3Dプリンターを活用すれば、木型や砂型そのものを短時間で作成することができるため、鋳造工程の短縮が可能になります。
作業工程を短縮できれば、納期の短縮につながるだけでなく、使用する材料や必要な人員を削減することができるため、結果としてコストを抑える効果も期待できます。
このように、スピードとコストの削減が求められる現代においては、手軽に活用できる3Dプリンターを鋳造工程に応用することが、ますます重要になってきています。
そのためには、3Dプリンターの技術について詳しく調べるだけでなく、切削や板金、鋳造といった従来の加工技術についても、あらかじめ十分に理解しておくことが求められます。
そして、これまで3Dプリンターを活用してこなかった業界においても、今後は積極的に3Dプリント技術を導入し、ものづくりにおける技術革新を推進していくことが望まれます。
筆者情報
- SOLIZEオンライン3Dプリント お役立ち情報編集部
- SOLIZEの3Dプリンター事業に従事する社員が、3Dプリンターの基礎知識や活用方法、活用例など、3Dプリンターに関する情報を発信します。